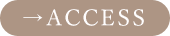コラム
子どもの歯磨きは何歳から?嫌がるときの対処法も

こんにちは。三重県伊賀市にある歯医者「SPT 矢谷歯科口腔医院」です。
「子どもの歯磨きはいつから始めればいいの?」「ちゃんと磨けているのかな?」「嫌がって磨かせてくれない」といった悩みをもつ保護者の方もいらっしゃるでしょう。
乳歯はやがて永久歯に生え変わるとはいえ、むし歯などのお口のトラブルを防ぐためには乳歯の時期からの口腔ケアがとても重要です。子どもの健やかな成長には、正しい歯磨き習慣を身につけることが欠かせません。
この記事では、子どもの歯磨きのスタート時期や、歯磨きを嫌がるときの対処法、仕上げ磨きをするときのコツについて詳しく解説します。子どもの歯磨きがうまくできずに悩まれている保護者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
子どもの歯磨きは何歳から始める?

まずは、いつから歯磨きを始めるべきかという疑問に答えていきましょう。子どもの歯磨きは、最初の乳歯が生えた時点からスタートするのが基本です。
多くの子どもは生後6か月ごろに下の前歯が生え始めるため、この時期が歯磨きデビューの目安となります。最初はガーゼや柔らかい歯ブラシを使い、お口の中に触れることに慣れさせることから始めましょう。
むし歯の原因となるミュータンス菌は、乳歯が生えることでお口の中に住みつきやすくなります。そのため、まだ食事がミルク中心であっても、しっかりとケアを行い、口腔内を清潔な状態に保つことが大切です。
奥歯が生えてくると、歯と歯の間に食べ物が挟まりやすくなるため、歯ブラシによるケアがより重要になります。歯磨き粉はフッ素入りのものを選ぶとよいですが、使用量はごく少量(米粒程度)に抑えるようにし、飲み込まないように注意が必要です。
2歳ごろになると、自分で歯ブラシを持ちたがるお子さんも増えてきます。この時期から自分で磨いたあとに保護者の方が仕上げ磨きをするという習慣を作ることで、子どもが自然に歯磨きを受け入れられるようになります。
子どもが歯磨きをするときのコツ

子どもが楽しく、そして正しく歯磨きができるようにするためには、いくつかの工夫が必要です。以下に詳しく解説します。
遊びの延長として歯磨きを取り入れる
小さな子どもにとって、歯磨きは退屈でつまらないものに感じやすい行為です。そのため、歯磨きを遊びや習慣の一部として取り入れることが大切です。
たとえば、お気に入りのキャラクターが描かれた歯ブラシを用意したり、歯磨きソングを流したりしながら磨くことで、楽しい雰囲気を演出することができます。アプリや動画など、歯磨きの時間をカウントダウンするツールを使うのもよいでしょう。
歯磨きを楽しい時間だと思ってもらえる工夫が、習慣化への第一歩になります。
歯磨きタイムをルーティンに組み込む
子どもが歯磨きをスムーズに受け入れるためには、いつもの流れの一部として生活習慣に取り入れることが有効です。
たとえば、お風呂のあとは歯磨きをする、寝る前の絵本の前に歯磨きをするなど、毎日決まった流れのなかに歯磨きを組み込むことで、自然と抵抗感が薄れていきます。習慣化されれば「やらなきゃ」と思う前に体が動くようになるでしょう。
声かけと褒め方を工夫する
子どものモチベーションを高めるためには、保護者の方による声かけやリアクションが大きな影響を持ちます。
磨く前には「ピカピカにしようね」といったポジティブな言葉で促し、磨き終わったあとには「よく頑張ったね」「きれいになったよ」としっかり褒めてあげましょう。
小さな子どもにとって、保護者の方に認められることは何よりの喜びです。このような声かけを通じて、歯磨きへの前向きな気持ちを育てることができます。
子どもが歯磨きを嫌がるときの対処法

どれだけ工夫しても、子どもが歯磨きを嫌がる時期はあるものです。ここでは、その際の対応策をご紹介します。
無理やり磨かない
歯磨きを嫌がる子どもに対して、力ずくで磨こうとするのは逆効果です。無理に押さえつけて磨こうとすると、歯磨きに対する恐怖心や嫌悪感が強くなり、ますます拒否するようになります。
どうしても歯磨きを嫌がるときは、無理に磨こうとせず、一度時間を置いてから再チャレンジしましょう。
口の中を触られることに慣れていない場合は、まずは遊びの延長で口元を触ったり、マッサージをしてスキンシップを取ったりするなど、段階的に慣れさせていくことが重要です。
歯磨きを嫌がる理由を考える
子どもが歯磨きを嫌がる理由は一人ひとり異なります。歯ブラシが硬くて痛い、歯磨き粉の味が好きではない、仕上げ磨きのときに無理な姿勢で不快に感じているなど、さまざまな要因が考えられます。
そのため、まずはどうして歯磨きを嫌がるのかを冷静に観察し、原因を取り除く努力が必要です。たとえば、歯ブラシのヘッドを小さいものに変える、柔らかめの毛にする、歯磨き粉を変えるといった工夫が有効です。
子どもの反応を見ながら、より快適な歯磨きタイムを作ってあげましょう。
一緒に歯磨きをする時間をつくる
子どもは大人の真似をすることが大好きです。保護者の方が楽しそうに歯磨きをしている姿を見せることで、子どもも「自分もやってみたい」という気持ちになります。
毎日同じ時間に親子で鏡の前に立ち、一緒に歯を磨く習慣をつけると、歯磨きは嫌な時間ではなく、楽しい時間として定着していきます。また、兄弟姉妹と一緒に歯を磨くのもよいでしょう。
子どもにとって歯磨きが孤独な行為ではなく、誰かと一緒に行うポジティブな活動になるような雰囲気作りが重要です。
歯科医院のサポートを活用する
ご家庭での対応に限界を感じる場合は、歯科医院で相談するのも一つの方法です。
歯科医院では、子どもが歯磨きや診察に慣れるためのトレーニングを行ってくれることがあります。また、定期的にプロによるクリーニングを受けることで、むし歯のリスクを減らすだけでなく、歯科医院への信頼感や安心感を育てることにもつながります。
歯科医師や歯科衛生士から歯磨きの方法や道具について具体的なアドバイスをもらうことで、ご家庭でのケアの質も上がるでしょう。
仕上げ磨きをするときのコツ

仕上げ磨きは、子どもが自分で歯を磨けるようになるまでは欠かせない重要なケアです。磨き残しを減らし、むし歯を防ぐためにも、保護者の方がしっかりとサポートしてあげる必要があります。
まず大切なのは、子どもが安心して身を任せられるように、落ち着いた環境で行うことです。明るい場所で行うと、磨き残しを確認しやすくなります。
使用する歯ブラシは、小さめのヘッドで柔らかい毛のものを選び、歯と歯ぐきに優しく当てて小刻みに動かすようにします。力を入れすぎると痛みを感じて、子どもが嫌がる原因になるので注意が必要です。
また、仕上げ磨きは1日1回、特に夜の就寝前に行うことが推奨されています。寝ている間は唾液の分泌量が減り、むし歯のリスクが高まるため、夜の丁寧なケアがとても重要です。
さらに、歯と歯の間の汚れは歯ブラシだけでは落としきれません。そのため、デンタルフロスの使用が推奨されます。特に奥歯や歯と歯が密着している部分は、食べかすが残りやすく、むし歯の原因になります。
子ども用のホルダー付きフロスを使うと扱いやすく、保護者の方も安全に使用できます。慣れないうちは無理をせず、子どものペースに合わせて少しずつ取り入れていきましょう。
まとめ

子どもの歯磨きは、単なる日課としてではなく、一生の健康を支える大切な習慣づくりの第一歩です。生後半年頃からのスタートが目安となり、成長とともに磨き方や接し方を変えることが求められます。
子どもにとって歯磨きが楽しく感じられるような工夫をしながら、保護者の方による仕上げ磨きでしっかりとサポートすることが重要です。
また、嫌がるときには無理をせず、子どものペースに寄り添うことが、長い目で見て歯磨きを習慣化するためのポイントです。必要に応じて歯科医院の力も借りながら、家族で協力して子どもの口腔環境を整えていきましょう。
正しい知識と関わり方が、将来の健康な歯と笑顔を守る大きな力になります。
お子さんのお口の健康を守りたいとお考えの方は、三重県伊賀市にある歯医者「SPT 矢谷歯科口腔医院」にお気軽にご相談ください。
当院の院長・副院長は口腔外科出身で、親知らずの抜歯やインプラント治療などを得意としています。虫歯・歯周病治療や矯正治療、入れ歯治療なども行っております。
当院は、地元の伊賀市だけでなく、名張市・亀山市・津市からも多くの患者様にご来院いただいております。歯に関するお悩みはぜひお気軽にご相談ください。
ホームページはこちら、ご予約・お問い合わせもお待ちしておりますので、ぜひご覧ください。あわせて公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。